2014年04月11日
R-Mapによる製品安全リスクマネジメント:日科技連
R-Mapとは、縦軸を「発生頻度」、横軸を「危害の程度」としたマトリクスの表を使ってリスクの大きさを表現する手法で、日本科学技術連盟の研究会で開発された手法です。詳細は、下記サイトに紹介されています。
http://www.juse.or.jp/reliability/103/
R-Mapの解説動画や、入門用のテキストの無料ダウンロード(個人情報の登録が必要)があり、非常に理解が進みます。
上述したようにマトリクスでリスクの大きさを評価するという考え方は、従来のFMEAで用いられていたRPNよりも柔軟で合理的な評価が可能ですので、非常に良い視点ですよね。製品安全の分野では、リスクアセスメントが必須ですが、R-Mapを使えば、リスクの大きさをうまく評価できるように思います。
http://www.juse.or.jp/reliability/103/
R-Mapの解説動画や、入門用のテキストの無料ダウンロード(個人情報の登録が必要)があり、非常に理解が進みます。
上述したようにマトリクスでリスクの大きさを評価するという考え方は、従来のFMEAで用いられていたRPNよりも柔軟で合理的な評価が可能ですので、非常に良い視点ですよね。製品安全の分野では、リスクアセスメントが必須ですが、R-Mapを使えば、リスクの大きさをうまく評価できるように思います。
タグ :日科技連
2014年04月10日
知識DBを使った安全設計:構造化知識研究所
安全設計支援ツールの調査で、知識の構造化というアプローチを活用する手法に出会いました。構造化知識研究所が開発したSSMという手法で、詳しくは下記サイトに紹介されています。
http://www.ssm.co.jp/ssm/index.html
構造化知識研究所のHPによると、この手法では、過去の失敗事例や一般的な故障の知識を体系的な知識DBに整理して、それらを装置や製品の設計で活用する仕組みが提供されています。
SSMとは、Stress-Strength Model(ストレス-ストレングス・モデル)の略です。このモデルは、一つ一つの故障の知識を構造化するための枠組みとされています。また、知識DBを活用するため、かなり本格的な支援ソフトウエアも開発されているようです。
SSMでは、まず、この知識の枠組みに基づいて構造化された知識(お役立ち度の高い知識)を豊富に整理し、その知識データを検索に役立つ辞書を使ってうまく引き出していくという点が特徴のようです。ポイントは「知識の再利用」。個別の報告書の中から、「不具合が起きた箇所」「起きた現象」「原因」などの核心部分を抜き出します。具体的には、問題となった箇所やパーツや現象、現象が発生する条件や、問題となった箇所やパーツが耐えられなかった理由を入力して内容を構造化し、知識として再利用できるようにします。
これらの情報をお互いに関連づけたり、技術者がふだん設計の際に接する言葉や状況と結び付けたりすることで、過去の教訓を生かしやすくなります。これなら製品の分野や設計部位が違っていても、状況が似通っていれば応用することができるでしょう。
GIGO(Garbage In, Garbage Out)という言葉があるように、無駄な情報をデータベースにして活用しようとしても全く役に立ちません。この手法は、FMEA、FTAなどなどの手法や、設計チェックリスト手法と合わせて利用すると、安全に対する設計支援になりそうです。安全設計に役立つ知識を構造化することによってこのような事も実現できるのでしょうね。
この手の知識DBは、誰がどのように構築してゆくのかという点がとても重要ですね。職場の身近なところにも、メンテナンスされていない雑草だらけのデータベースがあります。社内のさまざまなデータや経験を「見える化」し、かつ「使える化」することが課題になっています。月日が経つと技術も進歩して古いデータはあまり使えなくなるという話はよくあります。知識DBの内容を定期的に見直すのは大変ですが、大事なことのように思います。
いずれにせよ、知識の構造化手法では、基礎的な知識を登録して関連する情報をリンク付けしてゆけるようなので、若葉マークの新人向けの技術教育にも使えそうです。様々な知識や情報をつなげてネットワーク状に広げながら、そのつながりに構造をもたせるというのは大変なことだと思いますが、面白いアプローチですね。
構造化知識研究所のサイトには一般的な知識データベースがないようですが、メーカの各々で、自社の内部データを活用できるようにしているみたいです。新人教育で使える一般的なDBがあればいいですね。
http://www.ssm.co.jp/ssm/index.html
構造化知識研究所のHPによると、この手法では、過去の失敗事例や一般的な故障の知識を体系的な知識DBに整理して、それらを装置や製品の設計で活用する仕組みが提供されています。
SSMとは、Stress-Strength Model(ストレス-ストレングス・モデル)の略です。このモデルは、一つ一つの故障の知識を構造化するための枠組みとされています。また、知識DBを活用するため、かなり本格的な支援ソフトウエアも開発されているようです。
SSMでは、まず、この知識の枠組みに基づいて構造化された知識(お役立ち度の高い知識)を豊富に整理し、その知識データを検索に役立つ辞書を使ってうまく引き出していくという点が特徴のようです。ポイントは「知識の再利用」。個別の報告書の中から、「不具合が起きた箇所」「起きた現象」「原因」などの核心部分を抜き出します。具体的には、問題となった箇所やパーツや現象、現象が発生する条件や、問題となった箇所やパーツが耐えられなかった理由を入力して内容を構造化し、知識として再利用できるようにします。
これらの情報をお互いに関連づけたり、技術者がふだん設計の際に接する言葉や状況と結び付けたりすることで、過去の教訓を生かしやすくなります。これなら製品の分野や設計部位が違っていても、状況が似通っていれば応用することができるでしょう。
GIGO(Garbage In, Garbage Out)という言葉があるように、無駄な情報をデータベースにして活用しようとしても全く役に立ちません。この手法は、FMEA、FTAなどなどの手法や、設計チェックリスト手法と合わせて利用すると、安全に対する設計支援になりそうです。安全設計に役立つ知識を構造化することによってこのような事も実現できるのでしょうね。
この手の知識DBは、誰がどのように構築してゆくのかという点がとても重要ですね。職場の身近なところにも、メンテナンスされていない雑草だらけのデータベースがあります。社内のさまざまなデータや経験を「見える化」し、かつ「使える化」することが課題になっています。月日が経つと技術も進歩して古いデータはあまり使えなくなるという話はよくあります。知識DBの内容を定期的に見直すのは大変ですが、大事なことのように思います。
いずれにせよ、知識の構造化手法では、基礎的な知識を登録して関連する情報をリンク付けしてゆけるようなので、若葉マークの新人向けの技術教育にも使えそうです。様々な知識や情報をつなげてネットワーク状に広げながら、そのつながりに構造をもたせるというのは大変なことだと思いますが、面白いアプローチですね。
構造化知識研究所のサイトには一般的な知識データベースがないようですが、メーカの各々で、自社の内部データを活用できるようにしているみたいです。新人教育で使える一般的なDBがあればいいですね。
タグ :構造化知識研究所
2014年04月09日
HAZOPを使った安全性評価:インターリスク総研
HAZOPは化学プラントの安全性評価でしばしば使われる手法で有名です。昨今は医療分野などでも適用されているようです。HAZOPはハゾップと呼ばれ、HAZard and OPerability study の大文字部分の略称です。
HAZOPは、プロセス分析を行い、各プロセスにおける異常を予測して、そこから事故等の影響を解析して、必要な予防措置を実施することを支援する手法です。各プロセスの異常は、おもに定常状態からのズレをガイドワードというものを利用して検討する点が特徴的です。
HAZOPの特徴や、手法活用時の注意点などをまとめた資料を探していたところ、インターリスク総研のホームページの下記文書を見つけました。
http://www.irric.co.jp/risk_info/disaster/pdf/saigairiskjoho47.pdf
このレポートは、HAZOPを用いた安全性評価方法の解説で、HAZOPの活用に関わるQ&Aなどもあり、なかなか勉強になりました。具体例も掲載されていて、参考になります。また安全性評価手法は、そもそもHAZOP以外にも、FMEA、FTA、ETAなどいろいろありますが、それぞれの特徴を一覧にした表もあり、興味深い資料になっています。本当にこのような区別でよいかどうかは大いに議論すべきように思いますが。
HAZOPは、プロセス分析を行い、各プロセスにおける異常を予測して、そこから事故等の影響を解析して、必要な予防措置を実施することを支援する手法です。各プロセスの異常は、おもに定常状態からのズレをガイドワードというものを利用して検討する点が特徴的です。
HAZOPの特徴や、手法活用時の注意点などをまとめた資料を探していたところ、インターリスク総研のホームページの下記文書を見つけました。
http://www.irric.co.jp/risk_info/disaster/pdf/saigairiskjoho47.pdf
このレポートは、HAZOPを用いた安全性評価方法の解説で、HAZOPの活用に関わるQ&Aなどもあり、なかなか勉強になりました。具体例も掲載されていて、参考になります。また安全性評価手法は、そもそもHAZOP以外にも、FMEA、FTA、ETAなどいろいろありますが、それぞれの特徴を一覧にした表もあり、興味深い資料になっています。本当にこのような区別でよいかどうかは大いに議論すべきように思いますが。
タグ :インターリスク総研
2014年04月08日
製品の安全性確保に向けた取り組み:東芝
東芝は、製品の安全性確保に向けた取り組みを以下にて紹介しています。
http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/performance/customer/safety.htm
東芝グループは、2012年に、製品安全対策優良企業表彰(大企業 製造事業者・輸入事業者部門)で 優良企業表彰(商務流通保安審議官賞)を受賞しており、安全性確保に向けた取り組みにおいて、対外的な評価も高い企業です。
東芝の取り組み方針で興味深いのは、事故の未然防止という話だけではなく、事故の再発防止に対する積極性を強く打ち出していることだと感じています。
東芝グループの製品安全に関する基本方針の第6項に、
「事故原因を徹底的に分析し再発防止に努めます。」
があります。実際に、重大製品事故の再発防止に向けた情報共有化の取り組みを進めているそうです。
未然防止はいうまでもなく重要ですが、起きてしまった事故に対して反省を行い、次に生かす教訓をしっかりと得ることは、事故を無駄にしないためにも重要な取り組みです。とても意義深いと感じています。
もちろん過去の事故を分析するだけでは未然防止は不十分ですが、人間は経験もなく完璧に未然防止することはできません。だからこそ自社で保有する過去の事故やヒヤリハットを大切にして未然防止に必要な技術を補てんしてゆくのです。過去の事故からの教訓を共有しないで、未然防止を進めることはかなり難しいことですね。
http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/performance/customer/safety.htm
東芝グループは、2012年に、製品安全対策優良企業表彰(大企業 製造事業者・輸入事業者部門)で 優良企業表彰(商務流通保安審議官賞)を受賞しており、安全性確保に向けた取り組みにおいて、対外的な評価も高い企業です。
東芝の取り組み方針で興味深いのは、事故の未然防止という話だけではなく、事故の再発防止に対する積極性を強く打ち出していることだと感じています。
東芝グループの製品安全に関する基本方針の第6項に、
「事故原因を徹底的に分析し再発防止に努めます。」
があります。実際に、重大製品事故の再発防止に向けた情報共有化の取り組みを進めているそうです。
未然防止はいうまでもなく重要ですが、起きてしまった事故に対して反省を行い、次に生かす教訓をしっかりと得ることは、事故を無駄にしないためにも重要な取り組みです。とても意義深いと感じています。
もちろん過去の事故を分析するだけでは未然防止は不十分ですが、人間は経験もなく完璧に未然防止することはできません。だからこそ自社で保有する過去の事故やヒヤリハットを大切にして未然防止に必要な技術を補てんしてゆくのです。過去の事故からの教訓を共有しないで、未然防止を進めることはかなり難しいことですね。
タグ :東芝
2014年04月07日
事故が起きた後の対応:パナソニック 他
-いま一度、心からのお願いです。ナショナルFF式石油暖房機を探しています- これは、下記URLにあるメッセージです。
http://panasonic.co.jp/
パナソニックは2005年当時、松下電器でしたが、この石油暖房機で死亡事故が出たことが発覚し、ブランドは地に堕ちたといってよいほどでした。しかし、かの有名なお詫びCMで、社の深い反省と事故対応の固い決意を感じさせました。これが結果的に功を奏し、松下電器批判は徐々に終息してゆきました。
事故後に、保身が全面に出て、誠実さが見えない会社は、必ず批判の矢面に立ちます。シンドラー社は、2006年に高校生が死亡するエレベータ事故を起こしましたが、事故直後に謝罪を行わず、しばらく住民説明会も拒み続け、ずいぶん批判されました。
日本は、直接的な原因がどこにあるかに関わらず、事故を引き起こした製品の提供者は誠実に対応することが求められます。事故の原因に対する責任があるから謝罪するのではなく、そのような原因は不明でも、ともかく何よりも事故を起こしている結果に対して謝罪する誠実さが求められているのですよね。
http://panasonic.co.jp/
パナソニックは2005年当時、松下電器でしたが、この石油暖房機で死亡事故が出たことが発覚し、ブランドは地に堕ちたといってよいほどでした。しかし、かの有名なお詫びCMで、社の深い反省と事故対応の固い決意を感じさせました。これが結果的に功を奏し、松下電器批判は徐々に終息してゆきました。
事故後に、保身が全面に出て、誠実さが見えない会社は、必ず批判の矢面に立ちます。シンドラー社は、2006年に高校生が死亡するエレベータ事故を起こしましたが、事故直後に謝罪を行わず、しばらく住民説明会も拒み続け、ずいぶん批判されました。
日本は、直接的な原因がどこにあるかに関わらず、事故を引き起こした製品の提供者は誠実に対応することが求められます。事故の原因に対する責任があるから謝罪するのではなく、そのような原因は不明でも、ともかく何よりも事故を起こしている結果に対して謝罪する誠実さが求められているのですよね。
タグ :パナソニック
2014年04月06日
原発事故の経過と教訓の記録:東京電力
2011年3月11日に東日本大震災が発生し、その後の津波の襲来により東京電力福島第一原子力発電所では原子炉の炉心溶融(メルトダウン)が発生し、国際原子力事象評価尺度(INES)でレベル7という深刻な事故が発生しました。
事故発生直後ははっきりしていませんでしたが、1号機、2号機、4号機で水素爆発が発生して、メルトダウンの発生も確実視されてくると、テレビでは、事故のメカニズムも連日詳しく報道されるようになりました。
その後、津波対策、全交流電源喪失(ステーションブラックアウト)対策を中心に、東京電力と、その他電力会社は、原発の安全性を高める対策を実施しました。しかしそれぞれ緊急措置に過ぎません。本当の意味での対策は、事故の発生メカニズムをしっかり究明して、原発の各プラントの構成機器において、今回のレベルの地震や津波に対して、そもそもどのような備えが不足していたのかを検証しなければ、実施できないものです。
東京電力では、下記URLに、「福島第一原子力発電所事故の経過と教訓」を掲載しています。
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/outline/index-j.html
「教訓」などと聞くと、東京電力は一体どんなことを反省しているだろうととても興味が湧きます。これだけの大事故です。きっと従来のリスクアセスメントの反省に立って深い考察が行われているに違いないと思っていました。
ところが・・・、内容を見てとても残念でした。そもそも津波や地震で、そもそも踏ん張るべきプラント各部がなぜ故障したのか、東京電力の反省がありません。津波や地震が来たから機器が故障したという点からスタートし、その結果、故障が故障を呼び、結果、過酷事故に至ったという話をしているにすぎません。一体、何を教訓にしているのでしょうか。これでは、事故の再発防止すらおぼつかないですね。とても残念に思います。
事故発生直後ははっきりしていませんでしたが、1号機、2号機、4号機で水素爆発が発生して、メルトダウンの発生も確実視されてくると、テレビでは、事故のメカニズムも連日詳しく報道されるようになりました。
その後、津波対策、全交流電源喪失(ステーションブラックアウト)対策を中心に、東京電力と、その他電力会社は、原発の安全性を高める対策を実施しました。しかしそれぞれ緊急措置に過ぎません。本当の意味での対策は、事故の発生メカニズムをしっかり究明して、原発の各プラントの構成機器において、今回のレベルの地震や津波に対して、そもそもどのような備えが不足していたのかを検証しなければ、実施できないものです。
東京電力では、下記URLに、「福島第一原子力発電所事故の経過と教訓」を掲載しています。
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/outline/index-j.html
「教訓」などと聞くと、東京電力は一体どんなことを反省しているだろうととても興味が湧きます。これだけの大事故です。きっと従来のリスクアセスメントの反省に立って深い考察が行われているに違いないと思っていました。
ところが・・・、内容を見てとても残念でした。そもそも津波や地震で、そもそも踏ん張るべきプラント各部がなぜ故障したのか、東京電力の反省がありません。津波や地震が来たから機器が故障したという点からスタートし、その結果、故障が故障を呼び、結果、過酷事故に至ったという話をしているにすぎません。一体、何を教訓にしているのでしょうか。これでは、事故の再発防止すらおぼつかないですね。とても残念に思います。
タグ :東京電力
2014年04月05日
自動車アセスメント:国土交通省
車をこれから買うひとにとっては、デザイン、車内スペース、エンジン性能など価格に応じて色々検討すると思いますが、安全性能への関心も高まっています。特に「アクティブセーフティ技術」は重要な考え方です。詳しくは、こちらをどうぞ。
http://www.mazda.com/jp/technology/safety/active_safety/
購入検討している車がどの程度、安全性能をもっているのか、関心ありませんか?
そういうときは、国土交通省が開示している「自動車アセスメント(車種別安全性能比較評価一覧)」が参考になると思います。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02assessment/car_h23/index.html
様々な車種に対して、衝突安全試験や歩行者頭部保護性能試験などの試験を実施した結果が評価点で示されています。具体的な数字が出ていて、結構生々しい感じがしますが、安全性能を考える目安にできると思います。
任意保険をお忘れなく。。。
http://www.mazda.com/jp/technology/safety/active_safety/
購入検討している車がどの程度、安全性能をもっているのか、関心ありませんか?
そういうときは、国土交通省が開示している「自動車アセスメント(車種別安全性能比較評価一覧)」が参考になると思います。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02assessment/car_h23/index.html
様々な車種に対して、衝突安全試験や歩行者頭部保護性能試験などの試験を実施した結果が評価点で示されています。具体的な数字が出ていて、結構生々しい感じがしますが、安全性能を考える目安にできると思います。
任意保険をお忘れなく。。。
タグ :国土交通省
2014年04月04日
消費生活用製品のリコール:NITE(製品評価技術基盤機構)と消費者庁
― 安全とあなたの未来を支えます - これは、独立行政法人 製品評価技術基盤機構(通称:NITE)のキャッチフレーズです。テレビで家電製品が燃える試験の映像を見たこと、ありませんか?この映像の提供元が、NITEです。製品安全分野や化学物質管理分野など様々な分野で活動していますが、社告・リコール情報の開示は有名ですね。
http://www.nite.go.jp/jiko/index4.html
対象は、消費生活用製品等で、家電製品に限らず、事務用品(椅子とか)や衣料品(靴とか)も含まれます。消費生活用製品の詳しい定義はこちら。
http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/02.html
平成19年に消費生活用製品安全法によって、重大製品事故の発生を知った製造業者・輸入事業者は、国へ事故の情報を報告することが義務づけられ、平成21年からは消費者庁に報告されています。一方、非重大製品事故は、NITEに報告することになっています。(義務ではないですが。)
あちこちの行政機関にリコール情報が報告されることになっていて、わかりにくいですね。下記の経済産業省のページにもリコール情報が掲載されています。
http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html
製品事故に遭わないために、消費者が見るべき情報サイトは一本化してほしいものです。
http://www.nite.go.jp/jiko/index4.html
対象は、消費生活用製品等で、家電製品に限らず、事務用品(椅子とか)や衣料品(靴とか)も含まれます。消費生活用製品の詳しい定義はこちら。
http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/02.html
平成19年に消費生活用製品安全法によって、重大製品事故の発生を知った製造業者・輸入事業者は、国へ事故の情報を報告することが義務づけられ、平成21年からは消費者庁に報告されています。一方、非重大製品事故は、NITEに報告することになっています。(義務ではないですが。)
あちこちの行政機関にリコール情報が報告されることになっていて、わかりにくいですね。下記の経済産業省のページにもリコール情報が掲載されています。
http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html
製品事故に遭わないために、消費者が見るべき情報サイトは一本化してほしいものです。
タグ :NITE
2014年04月03日
自動車のリコール:国土交通省
国土交通省には、自動車のリコール情報が掲載されています。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/index.html
上記サイトによれば、リコールとは、設計・製造上の問題により安全確保のため自動車メーカ等が国土交通省に届け出て、自動車の回収・修理を行うものです。
具体的には、「道路運送車両の保安基準」というものがあって、それに適合していない又は適合しなくなる恐れがある状態で、その原因が設計または製作過程にあると認められるときに、自動車メーカ等が、保安基準に適合させるために必要な改善処置を行うことをいいます。
事故の芽はあるけれど、世間に開示して早急に対処しておけば、事故拡大は防げるという発想です。運悪く事故に逢ってしまったひとには全く役に立たない情報ですが、国交省が、安全な社会をつくる責任を果たすためには重要な情報開示ですね。
ちなみに、保安基準に適合するほどのものではないけれど、看破できないものに対して改善処置を行うことを「改善対策」と言われ、それにも該当しないが商品性や品質の改善処置を行うことを「サービスキャンペーン」と言われます。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/index.html
上記サイトによれば、リコールとは、設計・製造上の問題により安全確保のため自動車メーカ等が国土交通省に届け出て、自動車の回収・修理を行うものです。
具体的には、「道路運送車両の保安基準」というものがあって、それに適合していない又は適合しなくなる恐れがある状態で、その原因が設計または製作過程にあると認められるときに、自動車メーカ等が、保安基準に適合させるために必要な改善処置を行うことをいいます。
事故の芽はあるけれど、世間に開示して早急に対処しておけば、事故拡大は防げるという発想です。運悪く事故に逢ってしまったひとには全く役に立たない情報ですが、国交省が、安全な社会をつくる責任を果たすためには重要な情報開示ですね。
ちなみに、保安基準に適合するほどのものではないけれど、看破できないものに対して改善処置を行うことを「改善対策」と言われ、それにも該当しないが商品性や品質の改善処置を行うことを「サービスキャンペーン」と言われます。
タグ :国土交通省
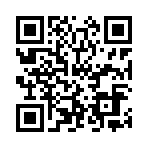
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン






