2014年04月06日
原発事故の経過と教訓の記録:東京電力
2011年3月11日に東日本大震災が発生し、その後の津波の襲来により東京電力福島第一原子力発電所では原子炉の炉心溶融(メルトダウン)が発生し、国際原子力事象評価尺度(INES)でレベル7という深刻な事故が発生しました。
事故発生直後ははっきりしていませんでしたが、1号機、2号機、4号機で水素爆発が発生して、メルトダウンの発生も確実視されてくると、テレビでは、事故のメカニズムも連日詳しく報道されるようになりました。
その後、津波対策、全交流電源喪失(ステーションブラックアウト)対策を中心に、東京電力と、その他電力会社は、原発の安全性を高める対策を実施しました。しかしそれぞれ緊急措置に過ぎません。本当の意味での対策は、事故の発生メカニズムをしっかり究明して、原発の各プラントの構成機器において、今回のレベルの地震や津波に対して、そもそもどのような備えが不足していたのかを検証しなければ、実施できないものです。
東京電力では、下記URLに、「福島第一原子力発電所事故の経過と教訓」を掲載しています。
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/outline/index-j.html
「教訓」などと聞くと、東京電力は一体どんなことを反省しているだろうととても興味が湧きます。これだけの大事故です。きっと従来のリスクアセスメントの反省に立って深い考察が行われているに違いないと思っていました。
ところが・・・、内容を見てとても残念でした。そもそも津波や地震で、そもそも踏ん張るべきプラント各部がなぜ故障したのか、東京電力の反省がありません。津波や地震が来たから機器が故障したという点からスタートし、その結果、故障が故障を呼び、結果、過酷事故に至ったという話をしているにすぎません。一体、何を教訓にしているのでしょうか。これでは、事故の再発防止すらおぼつかないですね。とても残念に思います。
事故発生直後ははっきりしていませんでしたが、1号機、2号機、4号機で水素爆発が発生して、メルトダウンの発生も確実視されてくると、テレビでは、事故のメカニズムも連日詳しく報道されるようになりました。
その後、津波対策、全交流電源喪失(ステーションブラックアウト)対策を中心に、東京電力と、その他電力会社は、原発の安全性を高める対策を実施しました。しかしそれぞれ緊急措置に過ぎません。本当の意味での対策は、事故の発生メカニズムをしっかり究明して、原発の各プラントの構成機器において、今回のレベルの地震や津波に対して、そもそもどのような備えが不足していたのかを検証しなければ、実施できないものです。
東京電力では、下記URLに、「福島第一原子力発電所事故の経過と教訓」を掲載しています。
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/outline/index-j.html
「教訓」などと聞くと、東京電力は一体どんなことを反省しているだろうととても興味が湧きます。これだけの大事故です。きっと従来のリスクアセスメントの反省に立って深い考察が行われているに違いないと思っていました。
ところが・・・、内容を見てとても残念でした。そもそも津波や地震で、そもそも踏ん張るべきプラント各部がなぜ故障したのか、東京電力の反省がありません。津波や地震が来たから機器が故障したという点からスタートし、その結果、故障が故障を呼び、結果、過酷事故に至ったという話をしているにすぎません。一体、何を教訓にしているのでしょうか。これでは、事故の再発防止すらおぼつかないですね。とても残念に思います。
タグ :東京電力
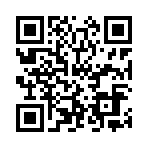
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン






