2014年04月10日
知識DBを使った安全設計:構造化知識研究所
安全設計支援ツールの調査で、知識の構造化というアプローチを活用する手法に出会いました。構造化知識研究所が開発したSSMという手法で、詳しくは下記サイトに紹介されています。
http://www.ssm.co.jp/ssm/index.html
構造化知識研究所のHPによると、この手法では、過去の失敗事例や一般的な故障の知識を体系的な知識DBに整理して、それらを装置や製品の設計で活用する仕組みが提供されています。
SSMとは、Stress-Strength Model(ストレス-ストレングス・モデル)の略です。このモデルは、一つ一つの故障の知識を構造化するための枠組みとされています。また、知識DBを活用するため、かなり本格的な支援ソフトウエアも開発されているようです。
SSMでは、まず、この知識の枠組みに基づいて構造化された知識(お役立ち度の高い知識)を豊富に整理し、その知識データを検索に役立つ辞書を使ってうまく引き出していくという点が特徴のようです。ポイントは「知識の再利用」。個別の報告書の中から、「不具合が起きた箇所」「起きた現象」「原因」などの核心部分を抜き出します。具体的には、問題となった箇所やパーツや現象、現象が発生する条件や、問題となった箇所やパーツが耐えられなかった理由を入力して内容を構造化し、知識として再利用できるようにします。
これらの情報をお互いに関連づけたり、技術者がふだん設計の際に接する言葉や状況と結び付けたりすることで、過去の教訓を生かしやすくなります。これなら製品の分野や設計部位が違っていても、状況が似通っていれば応用することができるでしょう。
GIGO(Garbage In, Garbage Out)という言葉があるように、無駄な情報をデータベースにして活用しようとしても全く役に立ちません。この手法は、FMEA、FTAなどなどの手法や、設計チェックリスト手法と合わせて利用すると、安全に対する設計支援になりそうです。安全設計に役立つ知識を構造化することによってこのような事も実現できるのでしょうね。
この手の知識DBは、誰がどのように構築してゆくのかという点がとても重要ですね。職場の身近なところにも、メンテナンスされていない雑草だらけのデータベースがあります。社内のさまざまなデータや経験を「見える化」し、かつ「使える化」することが課題になっています。月日が経つと技術も進歩して古いデータはあまり使えなくなるという話はよくあります。知識DBの内容を定期的に見直すのは大変ですが、大事なことのように思います。
いずれにせよ、知識の構造化手法では、基礎的な知識を登録して関連する情報をリンク付けしてゆけるようなので、若葉マークの新人向けの技術教育にも使えそうです。様々な知識や情報をつなげてネットワーク状に広げながら、そのつながりに構造をもたせるというのは大変なことだと思いますが、面白いアプローチですね。
構造化知識研究所のサイトには一般的な知識データベースがないようですが、メーカの各々で、自社の内部データを活用できるようにしているみたいです。新人教育で使える一般的なDBがあればいいですね。
http://www.ssm.co.jp/ssm/index.html
構造化知識研究所のHPによると、この手法では、過去の失敗事例や一般的な故障の知識を体系的な知識DBに整理して、それらを装置や製品の設計で活用する仕組みが提供されています。
SSMとは、Stress-Strength Model(ストレス-ストレングス・モデル)の略です。このモデルは、一つ一つの故障の知識を構造化するための枠組みとされています。また、知識DBを活用するため、かなり本格的な支援ソフトウエアも開発されているようです。
SSMでは、まず、この知識の枠組みに基づいて構造化された知識(お役立ち度の高い知識)を豊富に整理し、その知識データを検索に役立つ辞書を使ってうまく引き出していくという点が特徴のようです。ポイントは「知識の再利用」。個別の報告書の中から、「不具合が起きた箇所」「起きた現象」「原因」などの核心部分を抜き出します。具体的には、問題となった箇所やパーツや現象、現象が発生する条件や、問題となった箇所やパーツが耐えられなかった理由を入力して内容を構造化し、知識として再利用できるようにします。
これらの情報をお互いに関連づけたり、技術者がふだん設計の際に接する言葉や状況と結び付けたりすることで、過去の教訓を生かしやすくなります。これなら製品の分野や設計部位が違っていても、状況が似通っていれば応用することができるでしょう。
GIGO(Garbage In, Garbage Out)という言葉があるように、無駄な情報をデータベースにして活用しようとしても全く役に立ちません。この手法は、FMEA、FTAなどなどの手法や、設計チェックリスト手法と合わせて利用すると、安全に対する設計支援になりそうです。安全設計に役立つ知識を構造化することによってこのような事も実現できるのでしょうね。
この手の知識DBは、誰がどのように構築してゆくのかという点がとても重要ですね。職場の身近なところにも、メンテナンスされていない雑草だらけのデータベースがあります。社内のさまざまなデータや経験を「見える化」し、かつ「使える化」することが課題になっています。月日が経つと技術も進歩して古いデータはあまり使えなくなるという話はよくあります。知識DBの内容を定期的に見直すのは大変ですが、大事なことのように思います。
いずれにせよ、知識の構造化手法では、基礎的な知識を登録して関連する情報をリンク付けしてゆけるようなので、若葉マークの新人向けの技術教育にも使えそうです。様々な知識や情報をつなげてネットワーク状に広げながら、そのつながりに構造をもたせるというのは大変なことだと思いますが、面白いアプローチですね。
構造化知識研究所のサイトには一般的な知識データベースがないようですが、メーカの各々で、自社の内部データを活用できるようにしているみたいです。新人教育で使える一般的なDBがあればいいですね。
タグ :構造化知識研究所
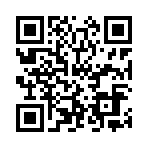
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン






